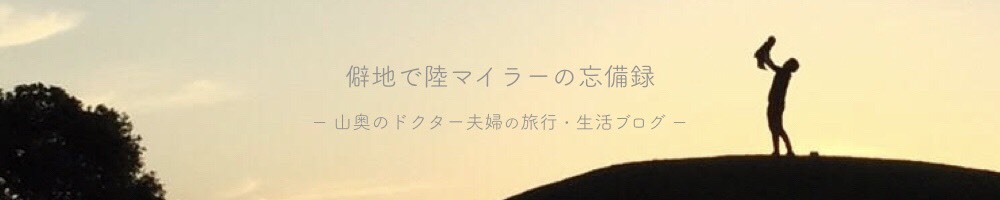ステロイドは強力な抗炎症作用と免疫抑制作用があり、どの科のDr.もお世話になる薬剤です。整形外科的には歴史的に、リウマチ関係の治療の歴史を変えた薬の一つになります。
ただその反面、長期使用に伴う副作用として、骨粗鬆症や易感染性など多くの副作用の報告があります。
副作用の話ばかりを聞いて、ステロイド使用にかなり嫌悪感を示す患者様も時にはおられますが、ステロイド使用を怠ったばかりに症状改善がなかなか得られないケースも経験的にあります。
今回はそれらステロイドの副作用の中でも、
ステロイド性骨粗鬆症についてまとめてみます。
ステロイド性骨粗鬆症はどんな人に起こりやすいか
骨粗鬆症は副腎皮質ステロイド治療における重要な副作用の一つです。
長期ステロイド治療を受けている患者の30-50%に骨折が起こるという報告もあります。
ステロイドユーザーであれば、高齢者だけでなく、小児にも骨折のリスクは上がります。そのため、骨折リスクでよく用いられるFRAXスケールとは別に、骨折リスクについて評価する必要があるのです。
骨折リスクを評価するにあたって、「骨折予測因子」があるかどうかを確認する必要があります。
骨折予測因子としては
年齢・ステロイド量(1mg以上)・骨密度・既存骨折・BP治療
が挙げられます。その中でも既存骨折が最も骨折リスクと相関するようです。
ステロイド投与量による骨折リスク
ステロイド投与量に依存してどの程度骨折リスクが増えるか調べた論文もいくつかみられています。
・2.5mg以下でも長期投与であれば椎体骨折が1.55倍になる
投与量が少なければ骨折リスクが増加しないというわけではないようです。
・5mg程度の投与量では、約3ヶ月の使用で骨折リスクが高くなる
ステロイド投与初期は骨代謝回転が低くなり、長期投与になると高回転が原因で骨折リスクが高くなります。ステロイド投与後3-6ヶ月に骨折リスクはピークを迎え、その後はプラトーになります。
投与中止後は徐々に骨密度は回復しますが、場合によっては数年骨折リスクは改善しません。
ステロイド性骨粗鬆症の機序
ステロイド骨粗鬆症の発生機序には、骨代謝系への直接作用と、内分泌系を介した間接作用の2つがあり、その両方から骨粗鬆症が進行すると言われています。
骨代謝系への直接作用
経口ステロイドは、間葉系幹細胞から骨形成系細胞の分化を抑制し、骨芽細胞と骨細胞のアポトーシスを促進します。すなわち、骨形成が著しく抑制されると同時に骨吸収が促進されるため、本来のスピードより早期に骨粗鬆症が進行することになります。
内分泌系を介した間接作用
経口ステロイドは性腺刺激ホルモン(GnRH)の産生を抑制するので、性ホルモン(エストロゲン、テストステロン)が減少します。そのため骨粗鬆症が進行します。また、腸管からのカルシウム吸収低下や尿細管からのカルシウム再吸収を抑制するため、カルシウム不足となるのも原因の一つです。
ステロイド性骨粗鬆症の治療
「ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン2014」に以下のような図が記載されています。

ステロイドユーザーには特に厳しめに骨折リスク評価が必要になります。上記図の評価を私も参考にはしていますが、あいにく勤務病院ではDEXA法でのXp撮影ができないため、厳密な評価は出来ずじまいです。その他の検査を代用して評価は行なっています。
第1選択は、アレンドロネート(フォサマック®︎、ボナロン®︎)
リセドロネート(アクトネル®︎)
ですね。BP製剤が基本となりますが、私は新規の脆弱性骨折などがみつかればテリパラチドを使用するなど、患者さんの状態に応じて選択肢を選ぶようしています。もちろん血液検査も適宜行い、現状を評価します。
まとめ
まずステロイドユーザーであればどんな人でも骨折リスクが上がる点は頭に入れておく必要があります。
骨折リスクを考慮する上で、1日5mgのステロイド内服があるかがひとつの境目です。
ステロイドは感染のリスクもあります。したがって、ステロイド内服中の骨折手術においても感染リスクが高くなります。
整形外科領域での手術で、感染が絡むと本当に大変です。
いずれにせよ、骨折しないようしっかりフォローしていくことが大事ですね。
骨粗鬆症の治療全般についてはこちらをお読みください↓
BP製剤、抗RANKL抗体と顎骨壊死の関連性についての記事もあります↓